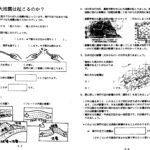必ず起こる、それは明日かもしれない
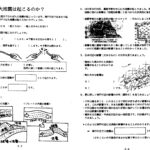 そう生徒たちに言い切ったのは、1995年1月13日の櫨谷中学での授業でした。「神戸で大地震は起こるのか?」というテーマで、「地震はなぜ起こるのか」を考えるためにもちだしたのは、プラスチック下敷き。「これに力を加えるとどうなる?」「曲がる」「はい。曲がります。もっと力を加えると?」「折れる」下敷きは突然壊れます。「同じように大地が割れるのが地震」「割れたところが断層」「断層が動くことによって地震が起こる」次に1891年の濃尾地震で現れた根尾谷断層のようす、日本列島にはたくさんの活断層があることを紹介します。そして「六甲山周辺の断層図」を持ち出して問います。
そう生徒たちに言い切ったのは、1995年1月13日の櫨谷中学での授業でした。「神戸で大地震は起こるのか?」というテーマで、「地震はなぜ起こるのか」を考えるためにもちだしたのは、プラスチック下敷き。「これに力を加えるとどうなる?」「曲がる」「はい。曲がります。もっと力を加えると?」「折れる」下敷きは突然壊れます。「同じように大地が割れるのが地震」「割れたところが断層」「断層が動くことによって地震が起こる」次に1891年の濃尾地震で現れた根尾谷断層のようす、日本列島にはたくさんの活断層があることを紹介します。そして「六甲山周辺の断層図」を持ち出して問います。
「神戸付近には多くの活断層があり最近は動いていません。ということは神戸で大地震は起こるでしょうか?」 生徒は「起こるかもしれない」「起こる可能性がある」と書いています。「違うよ。『必ず起こる』と書きなさい」「それは明日かもしれない、1000年後かもしれない」「その時神戸はグジャグジャになるの」「そうだ、『壊滅的な被害を受ける』と専門家が書いている」「どうしたらいいの?」 その時、チャイムが鳴りました。「大地震に備えてどうしたらいいかは、次の時間に考えましょう」“次の時間”は1月17日の予定で実現しませんでした。しばらくの休校をはさんで登校してきた生徒たちが書いてくれたことは「本当に地震が起こってしまった」「理科を勉強することの意味が分かった」「科学的に考えることが大切だと知った」でした。
授業をした私自身は、大地震の可能性を切迫した気持ちで受け止めていたわけでも、予感があったわけでもありません。「まさか!」が起こってしまったのです。
兵庫県南部地震をきっかけに「地震の活動期」に入った日本列島で、「いつでも」「どこでも」大地震が起こっても不思議ではありません。南海トラフ巨大地震も21世紀前半に必ず発生するともいわれます。阪神淡路大震災の教訓を次世代に伝え、次の地震に備えたいと思います。
2025-01-1