「しゅぱつ、シンコー!」
「しんごう、チューイ!」
「おおぎえき、2バンセン!」
電車の先頭の車両に、見習い運転士さんのこんな声がひびきわたるのは、12月ごろ。この声が、聞こえてくると、あっ、もうこの季節か、と思うようになった。
初めて聞いた時は、その声の大きさに驚いた。制帽の紐をきっちりと顎にかけ、緊張のあまり、微動だにしないで前を向いている見習い運転士さんの横には、指導役の先輩運転手さんが座っている。
細かな注意を受ける度の、「ハイッ」の返事の声も、また大きい。
はじめは、顔を見合わせてクスッとしていた車内の人たちも、やがて慣れてきて、本を読んだり、居眠りをし始めている。
「御影駅、3番線」
四月、見習い運転士さんは、運転士さんになって独り立ちしていた。
もう、あんな大きな声は出さない。
私は、まだ寒い頃に、車両いっぱいに響きわたっていた、あの彼らの声を、懐かしみながら思い出している。
こうして、たくさんの見習い運転士さんを眺めながら、季節を重ね、季節を見送っている。
そして、相変わらず、運転士さんのすぐ後ろのお気に入りの席で、締め切りに追われながらの原稿を書いている、ワタシ。
2024-3



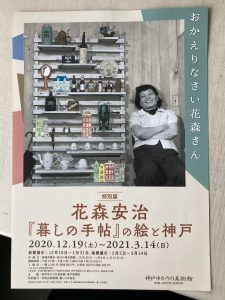 )などなしに、客観的で中立な批評がされていました。
)などなしに、客観的で中立な批評がされていました。 7月21日~9月24日
7月21日~9月24日

 阪神御影駅から、山の手に向かって、テクテク歩きました。JRの高架下を抜けると、弓弦羽神社の石柱があります。それから、まだ山手幹線を渡るとようやく参道が見えてきました。
阪神御影駅から、山の手に向かって、テクテク歩きました。JRの高架下を抜けると、弓弦羽神社の石柱があります。それから、まだ山手幹線を渡るとようやく参道が見えてきました。